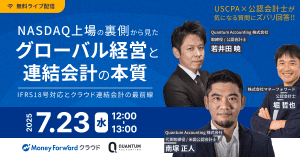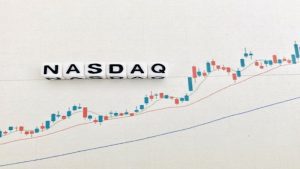はじめに
2025年、のれん会計をめぐる日本基準が大きな転機を迎えようとしています。政府の規制改革推進会議は、従来の日本会計基準における「のれん定期償却義務」の撤廃、あるいは「非償却と償却の選択制」への移行を含む答申をとりまとめ、企業会計基準委員会(ASBJ)に検討を要請する方針を打ち出しました。
この動きは、スタートアップのM&Aを促進し、企業の新陳代謝と国際競争力の強化を目指すものですが、その一方で、非償却モデルが抱えるリスクや課題も少なくありません。
本稿では、のれん会計をめぐるこの制度変更の背景、実務上の課題、そして国際的な潮流との関係について、欧米の実例を交えながら掘り下げてまいります。
日本型償却モデルが抱えていた課題
日本の会計基準では、M&Aで計上されたのれんは原則として20年以内の定額法で償却し、毎期販管費として計上することが義務付けられてきました。これは、のれんを「時間の経過とともに価値が減る無形資産」として扱う考え方に基づいています。
しかしながら、この償却モデルは、スタートアップを買収する企業やベンチャー投資家から、次第に制度的な足かせとして見なされるようになっていきました。特に、純資産が少なく、将来のシナジー効果を期待して買収されるスタートアップでは、のれんの金額が相対的に大きくなりがちであり、毎期の償却費が利益を大幅に押し下げてしまうからです。買収先企業の成長性が財務諸表に反映されにくくなり、M&Aが“損”に見えてしまう現象が発生していました。
また、IFRS(国際会計基準)や米国基準では、のれんは非償却とされており、定期的な償却は行われません。この違いは、国際的な会計比較を困難にし、日本企業が海外企業とのM&A競争で不利になる要因となっていました。
こうした実務上の不都合と国際比較でのハンディキャップを背景に、政府はのれんの会計処理に関して、国際基準に準じた減損モデルの導入に舵を切ったのです。
減損モデルへの期待とその現実
のれんを非償却とする「減損モデル」への移行は、表面的には理にかなった制度変更のように見えます。なぜなら、のれんはそもそも企業買収における将来期待を反映した対価であり、価値が毀損していない限り費用化すべきではないという考え方に基づいているからです。
非償却化されれば、企業は償却費を考慮せずに財務予測を立てることができ、買収判断が容易になります。また、IFRSやUS GAAPと同様の処理になるため、国際的な業績比較も行いやすくなり、海外投資家の理解を得やすくなるというメリットもあります。
ところが、この減損モデルには実務上の課題が多く存在しています。
まず問題となるのは、「減損の先送り」です。欧米でも、買収から数年が経過し、実質的に経営成果が出ていないにもかかわらず、会計上はのれんがそのまま残り続けるケースが多く見られました。企業が業績悪化を十分に認識してから、期末に一気に巨額の減損損失を計上する。いわゆる“Too Little, Too Late”と呼ばれる現象です。
例えば、2019年にクラフト・ハインツが154億ドルという巨額の減損を発表し、株価が急落した事例や、Sequential Brandsが2017年に3億ドルを超えるのれんの減損を突如発表した件では、米国証券取引委員会(SEC)が開示の適切性に疑問を呈しました。
加えて、減損テストはCGU(減損の判定・測定の単位となるキャッシュ・ジェネレーティング・ユニット)の識別、将来キャッシュ・フローの予測、公正価値評価など、非常に複雑でコストのかかる作業です。特に中小企業やスタートアップにとっては実施負担が重く、結果として制度疲労を引き起こしかねません。
世界の潮流と償却再評価の動き
減損モデルの限界が見え始めたことで、世界では再び償却モデルの意義が見直されつつあります。2020年に国際会計基準審議会(IASB)が実施したディスカッション・ペーパーでは、「のれんの償却再導入を検討すべきか」という問いに対して、多くのステークホルダーが肯定的な意見を示しました。
また、米国会計基準(US GAAP)を設定するFASBは2014年に非公開企業向けに、のれんの償却を最長10年間で認める簡便法を導入しました。このモデルでは、減損テストはトリガー事象が発生した場合のみで良く、運用負荷の低減と費用化の予測可能性の向上を両立しています。
欧州においても、EFRAG(欧州財務報告諮問グループ)などが「償却+減損のハイブリッドモデル」への回帰を提案しており、投資家側の理解も進んでいます。
こうした動きを背景に、日本でも今後「非償却モデルの単純導入」ではなく、一定の条件下での償却と減損を併用するハイブリッドな制度設計が検討される可能性が高まっていると思われます。
おわりに
のれんの会計処理は、企業の買収戦略と資本政策、さらには投資家との対話にまで深く関わるテーマです。単に制度をIFRSに近づけるだけではなく、日本企業の実務に適した形での透明性向上と、国際的な整合性の確保が求められます。
非償却モデルの導入にあたっては、減損要因の早期認識、テストの厳格化、情報開示の拡充といったガバナンス面の整備が不可欠です。同時に、企業側にも、自らの会計方針が投資家や市場にどう受け止められるのかという視点を持つことが求められています。
のれん会計をめぐる制度改革は、日本企業の将来の成長と市場での評価に直結する重大な論点です。今こそ、財務報告の本質に立ち返り、「わかりやすく、比較可能で、信頼される情報」を目指す取り組みが必要とされているのではないでしょうか。
弊社では日系企業のNasdaq上場のサポート、その他あらゆるクロスボーダー取引のサポートをさせていただいております。記事をお読みいただき、もっと詳しく話を聞きたいという方は、お気軽に弊社までご連絡ください。我々は、未来を見据えて今を走る皆様のお話をお伺いできることを楽しみにしております。またお伺いした中でサポートできることを提供いたします。相乗効果のある人と人のつながりを提供させていただきます。弊社へのお問い合わせは、お気軽に下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。